

(2024/03/05)
マッキンゼーの7Sはいろいろなところで引用され解説されている古くも有名な知見ですが、実はあまり適切といえない解説が多々見受けられて、とはいえ丹念に読み解くと意外と今日のビジネスを刷新できるかもしれない啓示に気づかされます。
提唱したピーターズやウォーターマンらは「私たちはこのフレームワークが非常に役立つことがわかった。組織の不調の原因を診断する際にも、改善のためのプログラムを策定する際にも、繰り返しその有用性を実証してきた。簡単に言えば、効果があるということだ。」と言い切っています。
提唱されたころのビジネス環境やニーズを分析し補正する必要はあるものの現在でもそれなりに活かせる知見でもありそうで、イノベーションを多産する組織になる手がかりとして、どう読み解けば温故知新できるか、考えてみる価値は十分にあります。
※引用文章はかなり機械翻訳結果そのままなので、多少ぎこちないのは許してください。
7Sはマッキンゼー・アンド・カンパニー社が考案したとされますが、同社のピーターズやウォーターマンらがエイソス(ハーバード大学ビジネススクール)の協力を得て1980年にSTRUCTURE IS NOT ORGANIZATIONという論文で提唱し、その後マッキンゼーの基本的な経営コンサルティングツールとして採用され普及した、というのがその経緯のようです。
A Brief History of the 7-S ("McKinsey 7-S") Modelに経緯が説明されています。
直前の1979年にはヴォーゲルが「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を出版し、パスカル(スタンフォード大学ビジネススクール)とエイソスが1981年に「The Art of Japanese Management」を共著出版しベストセラーになった頃でもあります。
なおパーソナルコンピュータのデファクト・スタンダードとなったIBM PC互換機の先祖であるIBM PCが発表されたのが1981年、基幹業務は1964年にやはりIBMがSystem/360を売り出して基幹業務のコンピュータ化はそれなり進んでいて、これからダウンサイジングの普及が始まろうかという時期でもあります。
「STRUCTURE IS NOT ORGANIZATION」では7つのSは構造、戦略、システム、スタイル、スタッフ、スキル、共有価値観の順で解説されていて、発表当時は共有価値観にあたるのは”Superordinate goals”(上位目標)で、後世に手が加えられて我々が知っている”Shared value”になりました。
最適な事業戦略を考える役に立つだとか、組織改革を実質的に進めることが可能になるといった効能で語られることが一般的なのですが、この論文の真意はまず組織の有効性を高める要素を見出すことであって、事業戦略や組織改革は言及している程度でそれほど踏み込んではいません。
また、7つのSの相互関連性の重要性を主張してはいますが、どう影響しあっていてその根拠は何なのか、についてはそれほど触れられてはいません。
自分の感覚だとどうしてもShared valueもしくはStrategyから読み解きたくなるのですが、原文は組織の有効性に問題意識があったこともあってお約束的にStructureからひもといているので、尊重しそれに倣います。
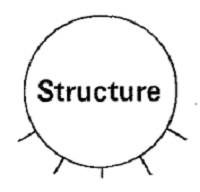
組織構造は戦略に従う(チャンドラー、1962年)と言われるように、機能的組織から分権化が進みマトリックス組織が普及し始めたのがこの頃で、ある一定のビジネス規模と複雑さの閾値を超えた企業は、それに対処するために機能・権限・責任を分散化せざるを得ないとします。
いっぽうで戦略が明確に組織設計の示唆を与えてくれるわけではないし、組織全体として一元管理しないとうまくない機能もあって、中央集権的なアプローチも必要だ、とも指摘します。
分権化と中央集権化(あるいは専門化と統合)のトレードオフの問題が表面化し始めている、という至極もっともな主張が組織構造に関する結論といえます。
ビジネス拡大戦略を進めると専門化した機能的組織が必要になり、さらに事業部制など分権化組織に移行しなければビジネスの複雑性を処理しきれなくなると、戦略と組織構造に強い関係を指摘するのは従来通りとして、加えて業務設計(systems)にも影響することを示唆しています。
大規模なビジネスにおいて案件が生じた都度に役割分担を考えていたのでは効率的な業務成果は期待できなくて、組織の効率性と組織構造に密接な関係があるのは言うまでもないでしょう。
イノベーションとの関係でも、ドラッカー(イノベーションと企業家精神)もダイナミック・ケイパビリティ(経済産業省製造基盤白書2020年版)も、與那原のダイナミック能力と両利きのマネジメントも、その実現のために組織構造の重要性に触れています。
論文でさらっと書かれていて見落としそうになる重要なヒントが、トレードオフ解消策として「一時的なオーバーレイを使用する」「効果的な"80年代の構造"は、"柔軟な"または"一時的な"と表現される可能性が高い」という記述で、オーバーレイとは、表面を薄く覆う、被せる、(別の情報を)重ね合わせる、といった操作のことです。
簡単にいえば、現存の組織を根本的構造的に変えるのでなくその機能を一時的に読み替えるなり拡張するなりして柔軟に機能付与して環境適応する、今の言葉でいえばプロジェクトを既存組織にオーバーラップする、といったニュアンスだと解釈できますが、詳しくは後ほど。
戦略とは、この論文の言葉を借りると
戦略とは、企業が顧客や競合他社といった外部環境の変化に対応し、あるいは変化を予測して計画する行動を意味する。戦略とは、企業が競争相手に対して自社の地位を向上させることを目指す方法である。
”私たちが独自の価値を創造する方法はこれです”といえるものが戦略だといいます。

それなり経営学も戦略論も組織論も普及し始めていながらしばしば東洋の新興勢力日本に苦杯を舐めさせられ、市場ポジショニング戦略や合理性追求経営だけでは優位に立てないことがわかり始め、とはいえ米国でも業績の良い企業もあってなにがその好調を支えているのか調べ考察解説したのがこの論文といえるでしょう。
戦略論としてはボストンコンサルティンググループが「金のなる木/花形/問題児/負け犬」からなるBCGマトリックスを提唱したのが1970年代、「差別化/コストリーダーシップ/集中」にポジショニングすることで優位になると説いたのはポーターで1980年、業界内の「リーダー/チャレンジャー/ニッチャー/フォロワー」の地位に基づいた戦略があるとしたのが1980年のコトラーでした。
このころの経営戦略論はまだ市場ポジショニング視点が主流で、コアコンピテンシ―(独自の強み)に着目した概念は一般的に普及してはいませんでした。
注目すべき記述は”フォーチュン誌は戦略に関する最近の記事の中で、注意深く計画された戦略のうち、おそらく90パーセントはうまくいかないとコメントしている。もしそうだとすれば、その失敗は実行の失敗であり、他のSへの不注意の結果であると推測される。”のくだりで、戦略そのものはさほど出来が悪いわけではなく、その実行過程で課題が顕在化し破綻する、という指摘です。
”世界中の名だたる大企業の中には、戦略があっても実行できない例があまりにも多い。彼らの構造にはほとんど問題はない。実行できない原因は、私たちのフレームワークの他の次元にある”という指摘は、戦略は他のSの影響を受ける、という主張に他なりません。
自分はナニゲに、現在の日本企業の戦略未達の多さをこの指摘に重ね合わせてしまいます。
経営戦略が「企業が組織や利害関係者に価値を提供し、市場で競争優位を確保するための戦略的な取り組み(Wikipedia)」である以上、組織活動を有効に行ううえで必要不可欠なのは間違いないでしょう。
イノベーションとの関係でいえば、まずそもそも従来生み出していなかった、または不十分にしか生みだせていなかった付加価値を創出するための新規の企てが戦略だから、経営戦略そのものがイノベーションだといってよく、かつ、定常的に付加価値を生産する通常業務とことなりむしろ一時的には経営資源を消費するイノベーションを企画し効果的に実行することも、戦略なくして行うことはできなくて、戦略とイノベーションは不可分な関係にあると言えます。
この論文では、当時すでに市場ポジショニング理論では企業業績が説明つかなくなっていて、”私たちが独自の価値を創造する方法はこれです”といえるものが戦略だという指摘や、この論文のskillのニュアンスから考えて、すでにコアコンピテンシ―の存在に気づいている気配を感じます。
この論文は多くの好調な企業の調査をしていて、それらにはすでに自社固有の強みを生かして事業している者もいるだろうから、それを目の当たりにしポジショニング理論の終焉に気づいていたとしてもおかしくはないでしょう。
他のSに留意せずに戦略実行しようとするのは無謀だとして、でもそれに加えて実行過程自体にも問題が起きていそうなのが昨今の戦略実行の敗因かもしれず、後ほど考察したいと思います。
広辞苑によれば、システムとは「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体。 組織。 系統。」だそうです。
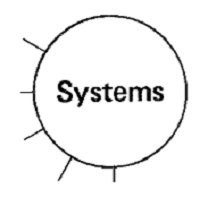
この論文では”システムとは、日ごと、年ごとに組織を動かしている、形式的なものから形式的でないものまで、すべての手続き”だといいます。
論文で示された事例は、事業ポートフォリオの中で最も魅力的なセグメントに重点的に投資しようとして、セグメント別の信頼できるコストデータがなく挫折した企業のケース、株主資本利益率(ROE)ツリー分析機能によって投資回収効率を判断し金利交渉を有利化した銀行のケース、など、ビジネス効果性を改善するうえで不可欠な業務プロセスの有無が業績を左右することを示唆します。
経営課題の優先順位付けが客観性合理性を欠き恣意的だと、経営意思決定がうまくいかず望ましくない状態から抜け出られない例にも触れていて、必ずしもsystemは業務プロセスなどのハードに限らないことも指摘しています。
”このモデルの中で、他の変数を支配する恐れがある変数があるとすれば、それはシステムかもしれない。”と明言し、組織が保有しているシステムの影響は甚大だと考えているようです。
ビジネスシステム全体つまり組織が、一部の業務プロセスやタスクに不備があったり十分機能を発揮しないために望み通りの有効性を発揮できなくなることもある、付加価値を生む要ともいえるシステム要素(業務プロセス・タスク)は些細なもののように思えても、すべて正しく設計し実行されなければ全体としてうまくいかない、というのがsystemで主張したいことだといえそうで、ごもっともとしか言いようがありません。
またシステムに人間が介在する場合の、恣意的な行動が引き起こす課題についての事例は、styleなどソフトSがその背景にあるとも思え、事業活動の結果として起きることは人の無意識が引き起こす行動の影響を受けうることを示唆しているかもしれません。
ドラッカー(イノベーションと企業家精神)もダイナミック・ケイパビリティ(経済産業省製造基盤白書2020年版)も、與那原のダイナミック能力と両利きのマネジメントも異口同音に、組織において目的達成のための業務プロセスが必要であることを指摘しています。
さらにいえば、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体・・・」という広辞苑の記述は、戦略やイノベーションをうまくやりきるためには、組織全体にわたり業務要素の有機的関係性を十分に解明し注意深く対処しないと変革がとん挫しかねないことを示唆すると思えます。
この論文でたぶん最も解釈に悩むのがstyleでしょう。
目に見える形がないぶん人によってとらえ方も異なって、経営スタイルだとか社風だとかいっても実体を掴みにくく、その根源が何で影響はどうなのか、解説しにくい概念です。
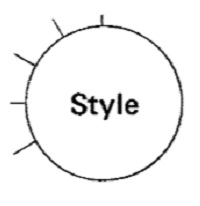
論文はstructureに次ぐ記述量でいろいろなケースを紹介し解説していて、しかしそれらから何が言えるのか、そう指摘する根拠は何なのか、ややぼんやりしていてやはり意をくみ取りにくい記述です。
”言葉ではなく、行動パターンが決定的なのだ” ”方向性の変化は多くの場合、「それ」が何であるかを本当に理解する前に、十分な数の人々がそれについて語ることから始まる”といった記述を深読みすると、フォーマルに同意されていないまたは明文化されていない行動パターンで影響の大きいものをstyleとみなしているように読み取れますが、著者らも問題の所在を明確に特定できていないきらいもあります。
”戦略的な可能性が、文化的な制約によって妨げられたり、スピードが落ちたりすることは何度もある”という指摘は、styleがかなり直接的に戦略実行の障害になりうることを示唆します。
企業買収や合併においてstyle不整合が失敗の原因になるものの、styleの変革を急ぎすぎるのも致命的だといいます。
組織が明示しているルール(規則や制度)とは別の、集団や組織の人々が準拠していて明文化されておらずフォーマルでないルールのことを、産業組織心理学で暗黙の規範と呼びます。
「ドミナント・ロジック」というもともとはおそらく認知心理学系の用語があって、直訳すると「支配的論理」なのですが、人々が共有する世界観、世界についての共通の見方や考え方、認識の仕方を指している概念です。
明示されずに暗黙のうちに共有している場合も多く、当事者自身が気づかないうちに、特定の論理に即して物事を見たり考えたり行動したりするのだといい、共有メンタルモデル(メンバー同士で共有されている体系化された知識や相互理解とそのイメージ)に近そうな概念です。
企業経営者もドミナント・ロジックを持つことがあって、事業を成功させるためのビジネスの組み立て方とその展開方法のその経営者なりの”勝ちパターン”とか、経営者の頭の中に学習された知恵として構築された認知マップをさす概念で、逆に経営者の勝ちパターンにフィットしていないような事業ではその勝ちパターンを横展開することができない以上、似たようなビジネスであってもうまくいかないと主張したのがPrahalad and Bettis (1986) だそうです。
Prahaladらの主張の内容についてはなぜ多角化は難しいのか(赤門マネジメント・レビュー7巻7号 2008年7月)を参照するとして、ピーターズやウォーターマンらが6年後に論文発表されるドミナント・ロジックという言葉を知っていたら、この論文ももう少しわかりやすかったかもしれません。
ここでは経営スタイルとか社風とか、暗黙のうちに共有されて人々の行動に影響しているルールとか論理、考え方、認識のうち、ビジネスの有効性にとって影響の大きいものをstyleの意図することだとして、これらは産業組織心理学の研究テーマの一つとして、原因や業績との関係が研究されているところです。
ドラッカーの企業家精神やダイナミック・ケイパビリティの「現状の企業行動が、環境や状況の変化に適合しなくなったかどうかを常に批判的に感知」など、イノベーション創出に影響するスタイル要素も指摘されているし、産業組織心理学でもコミットメントに促進される役割外行動のなかで経営革新促進行動という概念が知られています。
ちなみに良く知られているように、ピーターズとウォーターマンは1982年に大ベストセラー『In Search of EXCELLENCE』(エクセレント・カンパニー 超優良企業の条件 1983年講談社)を出版して、企業文化の重要性を説いています。
もっとも、マッキンゼー7Sにしてもエクセレント・カンパニーにしても、有名な割には正しく学んで実行できている組織はとても少なそうに思います。
この項目については、そもそもアメリカと日本で人材登用の考え方が全く違うという前提を理解したうえで解釈する必要があるでしょう。
アメリカではワーカーとマネージャとエリートは全く住む世界が違って、ここで議論しているstaffはエリートを意図しているようで、入社時点から経営中核人材候補として他とはまったく別次元の扱いを受けます。

人材を最もうまく活用している企業は、管理職を30代前半から半ばまでに積極的プログラムによって育成し集中的に管理している、最上級幹部が毎年数週間を上位数百人の育成に割いている組織もある、と指摘します。
トップクラスの企業では経営中核人材候補に手間ヒマ金をかけ、該当しない人材とは異次元といえる育成・社会化プロセスを経て基本的な価値観形成・実務能力強化をしているわけです。
組織の有効性を高めるうえでこの問題を無視する企業も多いが、無視できない変数であって、されど7つの変数の1つにすぎない、といいます。
アメリカでは、経営中核人材候補は入社時点ですでに体系的な経営知識・ノウハウを学んだ本物の即戦力で、いっぽう最上級幹部も経営学のうえに経営実務の修羅場での経験を積んだ本物の経営者で、日本の大部分の新卒や経営者とは全くレベルが違うのかもしれません。
しかも日本式の組織社会化プロセスは、新卒はもれなくオンザジョブトレーニングで下積みからスタートするから、「同じ釜の飯」を喰うそれなりの効果はあるものの、幹部候補を育てる仕組みでは決してありません。
次世代リーダーが育たないという経営課題は、経営陣の知識やスキルのレベルが低いから若手を育てられないし、若手の知識やスキルの高さを理解する能力がなく成長を正しく評価できないということを示しているにすぎません。
もし著者らが産業組織心理学に明るかったら、Staffを”変数の一つに過ぎない”とは言わず、人的資本経営は企業にとって極めて重要な戦略の一つだと言っていたかもしれませんが、まさに今日では組織の有効性におけるStaffの重要性が再認識されているといえるでしょう。
目的意識を持ち体系を完全に身につけ職務権限バランスを取れるメンバーや、両利きのリーダーシップやマネジメントができる経営層がイノベーションに必要だというのがドラッカーや與那原の指摘で、いわずもがな人的資本経営もイノベーションをリードできる人材育成を目指していると言えます。
7Sのなかでは比較的理解しやすいのがskillsで、それまでの市場ポジショニング理論では企業の業績を説明しきれないことに感づいていて、資源ベース理論でいうコア・コンピタンスに近いニュアンスで言及しています。
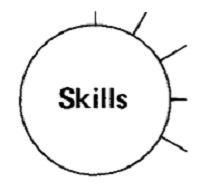
経営状況の転換に直面する組織は、往々にして戦略的な焦点の転換以上のことをしなければならず、圧倒的な新しいスキル(dominating capability:支配的能力)を追加する必要があると指摘します。
しかも新しいスキルを得るためには古いスキルの棄却が必要な場合もあるとし、組織としてのアンラーニングやサンクコスト(埋没費用)負担の決断が必要なことを示唆しています。
重要な新しいスキルが確実に根付き、成長できるように、古いスキルとそれを支えるシステム、構造などを淘汰することが必要だといいます。
昨今ではケイパビリティつまり企業特有の強みが企業の業績の源泉だというのが一般的認識で、さらに環境変化に合わせて強みを変化できる能力がダイナミックケイパビリティです。
組織が自らの優越的スキルを廃棄するのが容易でないことは、クリステンセンがイノベーションのジレンマで指摘しているとおりですが、ドラッカーが「イノベーションと企業家精神」で指摘したように「活力を失った、陳腐化した、生産的でなくなったものの廃棄を制度化」しなければならないでしょう。
論文の当時もそれはそれで日本の追い上げという大きな経営環境変化があったわけですが、昨今では環境変化が日常茶飯事になり始めていて、新しいスキルの獲得つまりイノベーションは避けて通れないと言えます。
資源ベース理論ではシステムや組織構造などもコア・コンピタンスになりうるので、逆に言えば古いシステムや構造自体が陳腐化していないか、費用をかけて構築したものももったいないと思わず、常時その適否を判断する必要があります。
もっとも現有の優越的スキルが構築され運用される段階で多くの知見や周辺ノウハウが蓄積され、それらは新たなスキルの構築に有利に働くことも少なくないので、ノウハウ再資源化の能力は確保したいところです。
Style、Staff、Skill、Strategy、Structure、Systemの6つのSに囲まれ7Sの中心に据えられたのがSuperordinate goalsで、後日Shared value(共通価値観)に改定されます。

”従来の形式的な企業目標の表明を超える一連の価値観や願望を意味し、多くの場合、文書化されていない”ものだといいます。
”従来の形式的な企業目標の表明を超える一連の価値観や願望を意味し、多くの場合、文書化されていない。上位目標は、ビジネスを構築するための基本的な考え方である。その主要な価値観である。”といいまた”将来の方向性に関する広範な概念”とも言っています。
組織としてのアイデンティティのような位置づけといえそうで、これが確立されていることが重要だと示唆しています。
”上位目標は数学的体系における基本定理のようなものである” ”目標は、そうでなければ変化しがちな組織の力学に安定をもたらす。他の6つのSとは異なり、上位目標はすべての、あるいはほとんどの組織に存在するわけではないようだ。しかし、優れた業績を上げている組織の多くには、この上位目標が存在する。”といい、他のSの土台となりバランスを取りながら改善するうえでなくてはならないと考えているようです。
Superordinate goalsからShared valueに改定される経緯、各々の意図の違いについて情報を探し出すことができなかったのですが、文中の”AT&Tの「ユニバーサル・サービス」目標、IBMの「顧客サービス」への強い意欲・・・”といった例示からして、組織のコアコンピタンスをより強化し磨き上げて業界ナンバーワンを目指す意思表明こそがSuperordinate goalsなのでしょう。
いっぽう別の視点でこの時代をふりかえると、コトラーのいうマーケティング2.0が1970〜1980年代、マーケティング3.0が1990〜2000年代だから、消費者中心マーケティングから人間中心マーケティングに変わり始める時期にあたります。
Superordinate goalsは消費者中心マーケティングのもとでの「自分が目指したい将来像」としての目標で、Shared valueは人間中心マーケティングを見据えた「社会が自分に求める自分のあるべき姿」としての目標だったのかもしれません。
今でいえばパーパスとかミッションとかクレドとか、必要であればマーケティング4.0や5.0の味付けも加味した、そういった「ありたい将来像・自分像と社会的存在価値」が該当するのだと考えておくのがよさそうです。
パーパスとかミッションとかクレドとかいったものが組織に浸透したとしても、電卓をたたくスピードが早くなったりアイデアが次々に降ってくるとは考えにくく直ちに組織の有効性が改善するわけではないのですが、産業組織心理学研究では組織文化や経営理念の浸透・価値の共有によって情緒的コミットメントが高められることが知られていて、コミットメントが高いと離職が抑止されるほか役割外行動(組織市民行動)が強化されることがわかっています。
役割外行動は正解のない課題への臨機応変な対応や経営革新行動など、職務上の義務的行動ではないものの組織に有益な行動で、これらが強化されることで間接的に中長期の組織有効性が高まることが期待できます。
むろん、課題解決に効果的な役割外行動でないと寄与は少ないので、適切で論理的に正しくセオリーに合った行動を取る必要があって、そのためには正しい知的な基礎が不可欠だから、単純に共通価値感の浸透度と組織有効性に単純明確な相関は観察されにくいのかもしれません。
イノベーションも容易に実現できるものではなく、組織目標が個人の腑に落ちてコミットでき本人にとって意義が感じられないと、内的報酬としてのやりがいが感じられなくなったり失敗でモチベーションが減退し、バーナードが指摘する目標の二重性(組織人としての目標と個人としての目標の乖離)が影響して、取り組む意欲は損なわれるでしょう。
この論文は、
これらの変数は、大きな変化を指揮する上で、少なくとも戦略や構造と同じくらい重要であり、実際、必要な、あるいは望ましい変化を達成するためには、ほとんど不可欠であると考える。システムの転換、スタッフに対する大規模な再教育プログラム、あるいは新たな上位目標に対するトップからボトムまでの熱意の創出には、何年もかかる可能性がある。戦略や組織の変化は、表面的にはもっと早く起こるかもしれない。しかし、真の変革のペースは、7つのSすべてに連動している。
最も強力で複雑なフレームワークは、私たちに相互作用と適合に集中することを強いる。組織の方向転換に必要な真のエネルギーは、モデル内のすべての変数が整列したときに生まれる。私たちのアソシエイトの一人は、私たちのダイアグラムをコンパスと見立てている。"7つの針がすべて同じ方向を向いているとき、あなたは組織化された企業を見ることになる "とコメントする。
と結論しています。
「7つの針がすべて同じ方向を向いている」ためには、何よりまずShared value(共通価値観)が浸透していることが不可欠でしょう。
多くの好業績企業の観察の結果見出されたのが7Sだし、今日的に再解釈しても納得感があるのですが、ではどうすれば7Sをバランスよく改善して高業績を上げるか、やはりというか残念ながらその手法に触れられているわけではありません。
でもおぼろげながら方向性はつかめそうで、さらに考えていく出発点にはできそうです。
なお深く解説する気がないのだからわざわざ追記しなくてもいいのですが、昨今ではオープンイノベーションやユーザー・イノベーション、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)などの重要性が叫ばれていて、それを考えるとSupply Chainとかstakeholderも無視できない要素なのかもしれず、経営環境や業界によっては8Sとか9Sとか考慮する必要があるかもしれません。